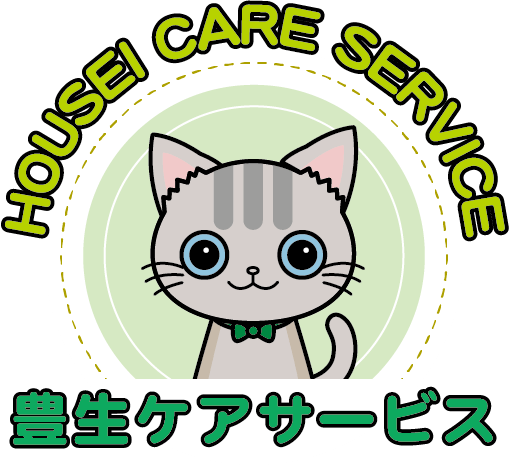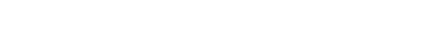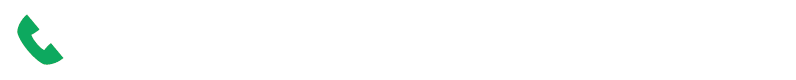9月の第3月曜日は「敬老の日」。長い人生を歩んでこられた高齢者に感謝し、その知恵や経験に敬意を表する日です。かつては三世代同居が当たり前で、家族や地域のつながりの中で自然に支え合いが行われていました。しかし、核家族化や単身世帯の増加により、高齢者が一人で暮らすケースも少なくありません。
こうした背景から、今あらためて「地域で高齢者を支える」という視点が大切になっています。
ひとりを支える“見守り”の力
高齢者にとって安心して暮らすためには、日常的なちょっとした声かけや見守りが大きな支えになります。ご近所同士の「おはようございます」の一言や、スーパーでの「今日は暑いですね」といった会話が、孤独を和らげるきっかけになります。
多様な支え方がある
支援といっても、特別なことをする必要はありません。買い物の際に重い荷物を持つお手伝いをすること、地域のサロンやイベントに一緒に参加することも立派な支え合いです。また、自治体やボランティア団体が行う見守り活動や配食サービスなど、制度や仕組みを活用することも大切です。
「支えられる側」から「支える側」に
高齢者自身が地域活動に参加し、世代を超えた交流を持つことも重要です。園児との交流や伝統文化の伝承、ボランティア活動など、経験を生かして地域を豊かにする役割を担うこともできます。
まとめ
敬老の日は「高齢者に感謝する日」であると同時に、「地域でどのように支えていけるか」を考えるきっかけにもなります。誰もが安心して年を重ねられる社会をつくるために、私たち一人ひとりができる小さな行動を、今日から始めてみませんか。