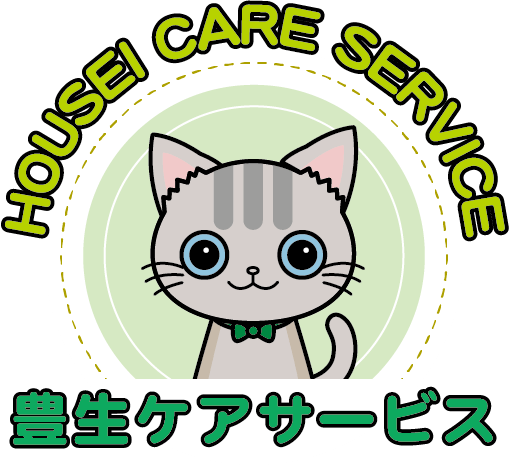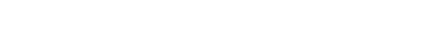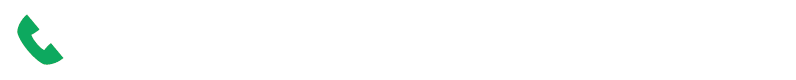はじめに
日本は地震・台風・豪雨など、自然災害が多い国です。特に洲本市をはじめ淡路島の地域は、瀬戸内海に面しながらも台風や高潮、土砂災害などの影響を受けやすく、「もし災害が起きたらどうなるのか」という不安を抱える方は少なくありません。
在宅で高齢者を介護しているご家庭では、避難の難しさや医療・介護サービスの中断など、災害時に直面する課題はさらに大きくなります。特に要介護の方がいる家庭では、普段の介護を災害時にもどう維持できるかが大きなテーマとなります。
そこで今回は、洲本市・淡路島で暮らす皆さまに向けて、災害時の在宅介護で備えておきたいことを詳しくご紹介します。
1. 災害時の在宅介護が抱えるリスク
在宅介護中の災害では、次のようなリスクが考えられます。
- 避難の困難さ:車椅子や歩行器を使う方、寝たきりの方はすぐに避難ができない。
- 医療機器の停止:在宅酸素や電動ベッド、吸引器などは停電で使用できなくなる。
- 介護用品の不足:おむつや介護食が流通しなくなると生活に直結した影響が出る。
- 介護サービスの中断:訪問介護や訪問看護が一時的に来られなくなる。
洲本市のように台風や豪雨の影響を受けやすい地域では、道路が寸断され外部からの支援が届きにくくなることも想定されます。そのため「行政や事業所の支援が届くまでの数日間を自力でしのぐ備え」が欠かせません。
2. 災害時に備えて家族や介護者で「情報を共有」する
介護を受ける方の情報は、災害時に大きな助けになります。
- 緊急連絡先リスト:家族、かかりつけ医、ケアマネジャー、洲本市役所の介護福祉課など。
- 医療情報:お薬手帳のコピー、服薬スケジュール、アレルギーの有無、既往歴。
- 介護情報:食事形態(刻み食・とろみ食など)、排泄の状況、使用している福祉用具。
これらを紙にまとめて防災バッグに入れておくと、避難先や病院でもスムーズに対応してもらえます。
また、事前に「在宅避難が可能か」「避難所へ移動するか」を家族で話し合い、状況に応じて判断できるようにしておくことも大切です。
3. 洲本市・淡路島で備えておきたい在宅介護用の備蓄品
生活必需品
- 水(1人1日3リットル × 3日分以上)
- 常温保存できる非常食(やわらかめの食品、ゼリー飲料、栄養補助食品)
- 懐中電灯、ラジオ、電池
介護用品
- 紙おむつ、尿取りパッド、おしり拭き
- とろみ剤、介護用食品、スプーン・ストロー
- 口腔ケア用品、手袋、マスク
医療・健康管理
- 常用薬(最低1週間分)とお薬手帳のコピー
- 吸引器や在宅酸素の予備バッテリー
- 体温計、血圧計、持病に必要な医療物品
介護が必要な方は一般の非常食では食べにくい場合があります。普段食べ慣れている介護食や、やわらかいレトルト食品を用意しておくと安心です。
4. 電源確保と福祉避難所の確認
洲本市や淡路島の地域では、停電が長引くケースも想定されます。在宅酸素や電動ベッドを使っている方は、非常用電源の確保が命に直結します。
- ポータブル電源や蓄電池を備える
- モバイルバッテリーやソーラー充電器を準備
- 電源が必要な機器の「優先順位リスト」を作っておく
また、災害時には洲本市内に福祉避難所が開設されます。ただし、一般の避難所とは違い「要介護高齢者や障害のある方」など配慮が必要な方が対象で、事前の申請や自治体との調整が必要な場合もあります。災害が起きてからでは手続きが遅れるため、日頃から確認しておきましょう。
5. 日頃からできる備えと地域とのつながり
災害への備えは一度準備して終わりではありません。
- 非常持ち出し袋の中身を定期的に点検・交換
- デイサービスや訪問介護スタッフと「災害時の連携」について話し合っておく
- 近隣住民や自治会と顔の見える関係を築いておく
洲本市や淡路島は地域のつながりが強い土地柄です。普段からご近所との関係を築いておくことで、災害時に「声をかけてもらえる」「助けてもらえる」安心感が生まれます。
まとめ
洲本市や淡路島で在宅介護をしているご家庭にとって、災害への備えは欠かせません。
特に重要なのは、
- 情報を整理・共有すること
- 介護に必要な備蓄を確保すること
- 非常用電源や福祉避難所を確認すること
- 地域や介護サービスとのつながりを持つこと
です。
災害は突然やってきます。しかし準備をしておけば、慌てず対応でき、介護を受ける方とご家族の安心につながります。
「もしもの時」を想像すると不安になりますが、備えがあれば不安を安心に変えることができます。洲本市・淡路島で在宅介護をされている皆さまも、この機会に防災対策を見直してみませんか。